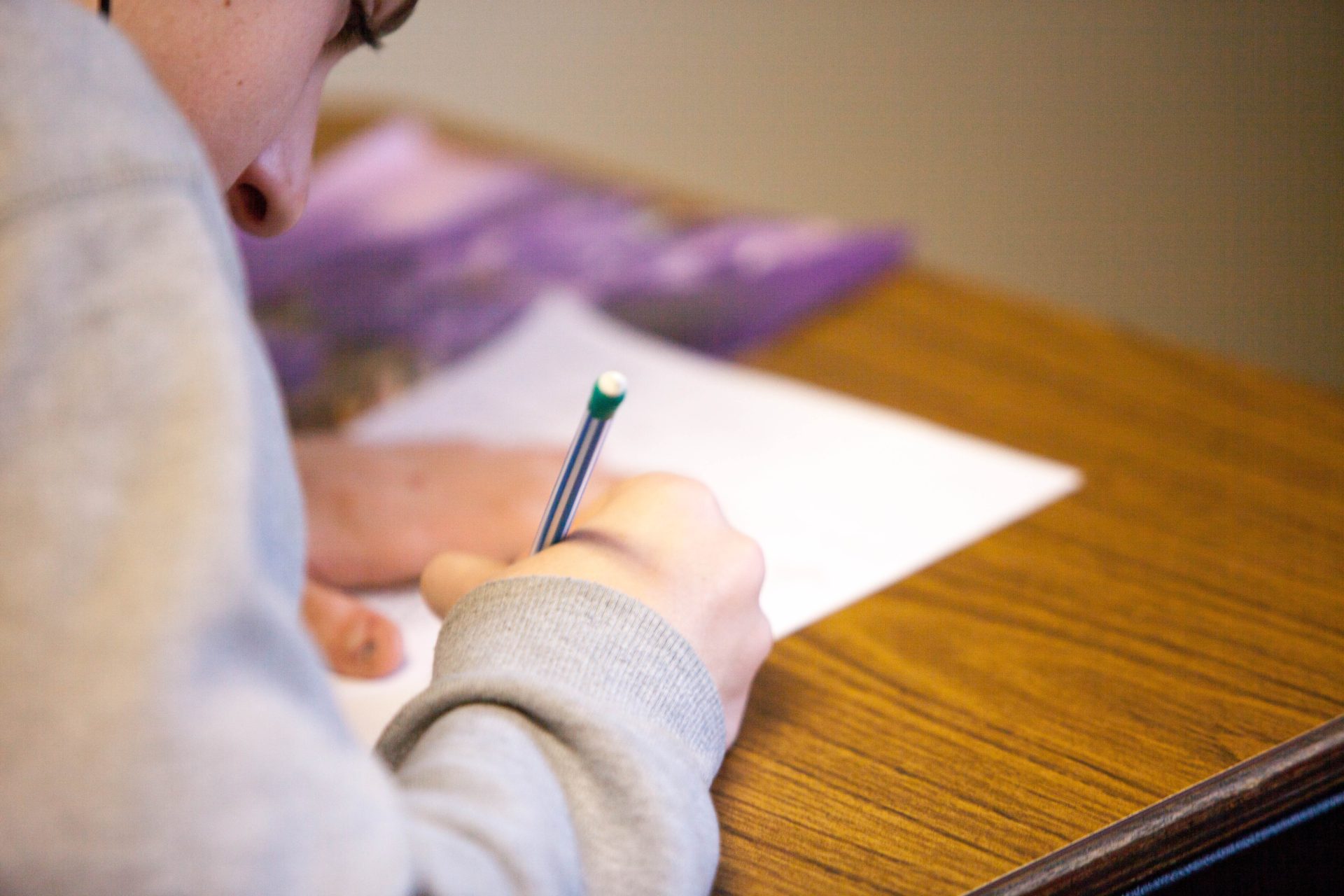こんにちは、ノマド税理士チャーリーです。
新年度を迎える4月、心機一転で資格取得を目指そうとする方も多いでしょう。
税理士になるための税理士試験は、例年8月の初めに行われます。
そこで、「4月から勉強開始」という短期間で、果たして税理士試験に合格できるのか、独学で税理士試験5科目合格した私がお答えします。
短期間で合格するコツについても、ご説明します。
【結論】専念なら短期間でも合格の可能性有り
4月から税理士試験の勉強を始めても、合格ラインには到達できます。
ただし、少なくとも次の条件はクリアしておきたいところ。
- 専念であること
- 通学でないこと
- 短期集中型であること
専念であること
一日10時間程度の勉強時間が取れないと、さすがに厳しいです。
詳しくは、下記で説明します。
通学でないこと
これは、どの専門学校も4月スタートで同年8月合格を目指すカリキュラムを用意していないためです。
あれば、通学でももちろん良いです。
ただ、通学時間も貴重ですから、独学のほうが逆に都合が良いかも。
短期集中型であること
はっきり言ってコツコツ派にはむきません。
残念ながら、要領が良い派でないと厳しいです。
小さな頃から、大した時間もかけていないのになぜかテストの点数だけは良かった、試験に一発合格する、「集中力があるね」とよく言われる、といったタイプが向いています。
理由:税理士試験合格ラインに必要な勉強時間から逆算

「短期間で合格」ということは、必ずしも「少ない勉強時間で合格」というわけではありません。
考え方はいたってシンプルで、まず、合格ラインに到達するといわれている最低必要勉強時間は確保します。
その上で、一日にさける勉強時間からかかる日数を算出するか、またはその逆で、かけられる日数から一日に必要な勉強時間を算出すればいいだけです。
税理士試験の科目合格に必要だと言われている勉強時間は、最も多いといわれている法人税でさえ、
計算600時間+理論600時間=1200時間。
※詳細は下記参照
【体験記】30歳超えて独学4年で税理士試験に合格した勉強法|試験の概要・選ぶべき科目
かけられる期間が4月から7月までと決まっている場合、日数は約120日間(8月の日数は計算に入れてません)。
ということは
1200時間÷120日間=10時間/日
一日、10時間の勉強時間が取れれば、合格ラインに達します。
途中で休憩2時間程度はさんでも、「朝9時~夜21時」ぐらい確保できればいけるでしょう。
理論暗記にかかる時間は、はっきり言って、方法と人によってかなり変わるので、一概に計算にかかる勉強時間の倍とは言えませんが、法人税の場合、少なくとも計算部分の勉強時間に一日5時間、確保すればよさそうですね。
すべて4月からの勉強で合格できた実体験
私は税理士試験5科目とも、3月までは勉強に一切手をつけず、ひたすら仕事と遊びに徹する、というポリシーのもと、すべて4月から勉強をスタートさせました。
一年目
- 専念期間:5月~8月の試験日まで
- 科目:簿記論・財務諸表論
- 到達度(自己判定):簿記論 70% 財務諸表論 60%
- 試験の出来(自己判定):簿記論 40% 財務諸表論 70%
- 結果:簿記論・財務諸表論 合格
税理士試験最初の登竜門、簿記論・財務諸表論は、自分でも半信半疑で独学にトライしてみました。
昼間は職業訓練校に通っていたので、平日のうち税理士試験の勉強に取れた時間は一日6時間程度。
期間トータルで恐らく600時間程度の勉強時間で、2科目突破できました。
これはかなりラッキーだったと思います。
もともと苦手意識のあった理論がある財務諸表論は、もう一年受けるつもりで挑んだのですが、試験を受けてみたら、あらびっくり。
簿記論がボロボロで、財務諸表論はイケた、と思いました。
ただ、結果は奇跡的にどちらも合格。幸先の良いスタートを切ることに。
簿記論・財務諸表論は5月からでも、合格レベルに達します。
二年目
- 専念期間:4月~8月の試験日まで
- 科目:法人税と消費税
- 到達度(自己判定):法人税 60% 消費税 70%
- 試験の出来(自己判定):法人税 50% 消費税 60%
- 結果:法人税・消費税 不合格(A判定)
理論は各科目、毎日だいたい2時間ずつとるのと、集中して覚える時間を定期的に作ってましたが、それぞれ300時間ぐらいしかとっていないと思います。
特に法人税の理論は苦手でした。消費税はまだ覚えやすいです。
計算は法人税:消費税=3:2、終盤は2:1ぐらいの時間配分で勉強し、結局、法人税:400時間、消費税:250時間程度の勉強時間で挑みました。
法人税はイチかバチかぐらいの勢いで受験、消費税は受験前まで結構自信があったんですが、本試験の計算で致命的なミスを犯して、どちらも不合格の結果に。
とはいえ、A判定だったので、目安とされる必要勉強時間よりは少なかったものの、合格ラインには乗りましたね。
4月からの勉強スタートで、次はイケそうだな、と不合格にもかかわらず自信をもっていました。
三年目
- 専念期間:4月~8月の試験日まで
- 科目:法人税と消費税
- 到達度(自己判定):法人税 70% 消費税 90%
- 試験の出来(自己判定):法人税 60% 消費税 80%
- 結果:法人税・消費税 合格
前年と同じようなペースで、気持ち理論多めで勉強しました。
前年と合わせると、結局、計算の勉強時間は、法人税400時間+400時間=800時間、消費税250時間+250時間=500時間、となります。
ただ、短期集中型のデメリットはすぐに忘れてしまうということでして、ベースの蓄積が思った以上になく、4月からまた新たに勉強し直した、ぐらいの感覚でした。
とはいえ、計算問題を解きだすと、「あぁ、これやったやったー」と感覚が戻ってくる場面もありましたが。
本試験については、法人税は微妙なラインでしたが、消費税はかなりの自信があり、結果はどちらも無事合格。
4月からの勉強スタートで十分間に合うな、と確信しました。
四年目
- 専念期間:4月~8月の試験日まで
- 科目:事業税
- 到達度(自己判定):事業税 90%
- 試験の出来(自己判定):事業税 80%
- 結果:事業税 合格
法人税と消費税の2科目平行を乗り越えると、楽勝でした。
同じ科目だけ勉強すればいいんですから。
ちょっと気持ちが緩んで、一日8時間程度、休みもかなり取りつつ勉強していました。
理論:400時間、計算500時間程度。
自分でいうのもなんですが、かなり仕上げた状態で受験に挑み、本試験も会心の出来で、結果、官報合格を果たしました。
ボリュームの少ない1科目だけなら、4月スタートの勉強で十分です。
税理士試験に短期間で合格するコツ

- 過去問題集を最初に読み込む
- 問題集(アウトプット)中心に勉強する
- 細かい論点は、切り捨てる
- 本試験のヤマをはる
過去問題集は、最初に問題と解答をよく読んで、傾向を把握し、到達点を設定します。
試験に出そうなところのみ勉強する勢いで、「問題集を解きまくる」アウトプット中心に勉強をすすめます。
まずは、細かい論点はほぼ無視。時間があったら目を通すぐらいで良いです。
試験直前、ある程度ヤマを張るのも大切です。
試験を出す側の気持ちになって、どんな論点をどんな風に出してきそうかイメージしてみましょう。
前年に出た問題は同じような形では出ないし、細かい論点はたぶん出ないはず(断言はしませんが)。
あとは、運も大きな要素です。
ここ出そうだな、と思った論点が見事あたることも結構ありました。
まとめ
というわけで、「4月から勉強開始=4か月間」という短期間でも、税理士試験に合格する可能性は充分ある、ということがわかっていただけたかと思います。
上記のとおり、必要な勉強時間さえ確保できれば、簿記論・財務諸表論はかなりの確率で大丈夫。
税法科目に関しては、ボリュームの大きい法人税か所得税で短期合格できれば、残りの税法も軽くこなせるはず。
一番大切なのは、「必ずできる」と信じてモチベーションを下げることなく8月まで突っ走ること。
ただ、数回失敗したら、方向転換も考えましょうね。
通学・通信・オンライン講座など、十分リサーチした上で自分にあった勉強法を見つけるのがベストです。
特に、下記オンライン講座では、効率的な教材・内容になっていると評判なので、無料で試してみるのも一考。思っているよりかなり安く、下手したら独学でかけた費用ぐらい・・・
悩むよりまずは行動した方から、未来が具体的に見えてきますよ。
少しでも参考になれば幸いです。